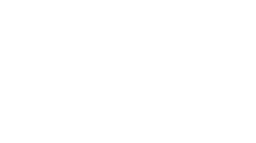2024年03月15日
不安について 第3章:日常生活を生きる生活者としての不安と死について
不安は先ほど述べたように、日常生活の中では不確実な未来に向けて「安全に生きたい」という生きることの緊張と同時に、失敗への強い恐れの葛藤からも生じます。ただ不安の対象が漠然としていて、明確ではありません。例えば年を取り、死が近づくことも不安を生み、怖くなります。不安が強い時、ICDでは「全般性不安障害」と診断されます。
もちろん幸せに生きている人は当然多くいます。ここではテーマ上、不安を持つ人の話を中心にします。
若い人では、将来へのさまざまな不安を抱えます。生活や経済面への不安と、人間関係への不安が中心です。仕事の問題や子供の育児、親同士の交流、実家との関係など。病気やけが、事故も心配です。生きていくことは多くの不安と隣り合わせなのです。
前章と重なりますが、特に、軽いものでも幼少期の家庭での虐待や学童期のいじめ、コンプレックスなどから生じたトラウマは強い隠れた不安として、その後も人生に残るようです。生きにくい人生になります。
それは常に、「同じようなことが起こらないか」という不安として残ります。その不安が強いと、未来への失望感が生じ、希望が持てず、重荷を背負ったように生きる苦痛となります。対人恐怖、怯えなどが続き、外界が怖くて引きこもりなどに広がる場合があります。最近見られる災害の恐怖や、性的事件も同じように強い形でトラウマや不安を引き起こします。
意識に上らずに恐怖が湧いてきて、自然に状況を避ける行為をしてしまう場合も多いです。
そのような時、本人は生きるつらさから死も考えます。
また、現在が幸せであっても「この幸せが壊れること、次に何か不幸が訪れること」への漠とした不安感はどこかにある場合があります。
不安の解消には、性格傾向や考え方、伴侶の存在などが影響します。外来で診ていると、仲の良い夫婦が多いようです。夫や妻を互いにいたわる伴侶が多いです。夫婦で助け合って、家庭を築く価値観自体は昭和の時代から、平成、令和と移る中で同じでしょうが、行動面での実際の助け合い、特に男性の家庭への協力は現代は明らかに増え、昔と変わってきているように感じます。良い伴侶と友人からの助け合いがあることなどで不安の多くが解消されるところがあります。
こうした不安な人生を生きることの苦難を「四苦八苦」と表現する仏教の世界観には、世界が実は無であり固執する対象でないと述べ、そうした理解によって欲望や煩悩、不安から解放、解脱させることができると説いています。宗教としての信仰の問題とは別に奥深い理性的な思想哲学が基本にあるといえます。実践することは難しいでしょうが、不安を解消する根本の考え方の一つといえます。
またそれは、ハイデッガーの「存在」の思想の根源への回答に方向性は違うかもしれませんが一番近づいているといえます。人間と世界の関係で「世界内存在」である人間の「存在とは何か」という問いに対して、そもそも世界や存在そのものが無であると説いているからです。
不安の中で死と向かい合って生きる「現存在としての人生」に近いのは老年期の人生でしょう。特に死の問題が切実なテーマである老年期について考えてみます。
老年期には多くの人が不安を抱えています。不安のない人はいないといってもいいでしょう。将来、死は確実にやってきます。今日をどう生きるかは大きなテーマです。
両親と同居している一人娘や息子などの3人家族などで、子供が強い不安を抱える場合も多いです。両親が死ねば自分一人になります。将来の孤独への恐怖に襲われます。親もそれがわかるがゆえに心配します。そして何とか自分たちの健康を維持することが、人生の最大の目標と考えます。
初老期は家庭的には、仕事も退職し、自分の子供も成長し、現代では夫と妻の二人での生活の方が多いです。
ただ二人だけになると夫婦のお互いの価値観の違いに悩まされる場合も多いようです。
二人の新たな価値観が必要になります。
退職し時間が余り、暇であることは工夫しないとなかなか大変なようです。退職して1か月もすると生活に飽きてきます。
毎日が日曜日であることは自由ではあるけれども、何の刺激もない退屈な生活なのです。
それほど趣味の無い人がほとんどです。このまま人生が過ぎ、老化することへの不安を覚えます。何とか、社会参加やアルバイトでもしようと考えます。
女性の方の中に「こんなはずではなかった。」と思わせる夫の姿に失望を訴える方が多くいます。今まで何を信じて、ともに生きてきたのかと迷います。何を言っても変化しない夫に、不安よりも生きることの、寂しさが生じます。ただ、もし相手に何かあれば、「将来一人になるのだろうか」と思う自身の孤独への不安が別に生じます。
また、息子夫婦との同居では、孤独とは別に嫁に気を使い、嫌われることへの不安から気疲れする人も多くいます。
ただ、こうした問題は、夫の側から提起されることはほとんどありません。男性は社会の中で希望通りにならないことに我慢することを学び、また、現代とは違い、家庭人としての経験が薄く、家庭での生活の仕方に慣れていないからでしょうか。あまり、妻への不安を漏らしません。時に妻から見ると対外的な外面だけいいように見える夫の姿への怒りもあります。夫なりには孤独にならないための工夫といえます。また、女性には時にカサンドラ症候群(パートナーや家族など身近な人が発達障害などのためコミュニケーションが取れず、不安障害やうつ状態などの症状がでること)を訴える方もいます。
ともかく、料理や買い物でも散歩でも夫婦で一緒に行動することが、気持ちを一致させるうえで大事なようです。
老年期は近づく死を前に、不確実なまま生きつづけることへの不安が生じます。
「自分は将来何の病気にかかり苦しんで死んでいくのか」という不安、「どのような形で死ぬのか」「事故にあわないか、経済的に大丈夫だろうか」「周囲の人や子供に迷惑をかけたくないが、孤独も怖い」など共通の多くの不安の中で日々過ごしている方が多くいます。死が近いのに何が起こるか、将来がわからないからです。高齢者の生活こそハイデッガーの「現存在」として死を意識しながら生を精一杯生きている存在ともいえます。
高年の老年期では体が動かなくなると、精神的不安は高まります。体は老化しますが精神は老化しないからです。
そうした悩みの強い人の中には、「できれば人に迷惑をかけず、そっと早く目立たないように死にたい。いい方法はないだろうか。」と常に考えている方も多いです。長く生きることが幸せだとは全く考えません。無理やり長く生きさせられるよりも、自分で死を選べればいいのにと考える方も多いです(なぜ、日本の病院では無理にでも長生きさせようとするのでしょうか。欧米と価値観が違うようです)。
死を意識しながら、毎日をコツコツと生きていくことや生きる価値観、死後の世界への関心、あきらめなどそれぞれに工夫して生きる必要があります。これまでの自分の人生が何であったかと考えさせられたり、時に悔やむ場合も多いようです。
不安と苦しみの中で多くの高齢者は生きるのですから、健康の保持、話し相手とともに、信頼、安心できる世界観が必要になっている状況にあるといえます。
生きるために何かが必要なのです。
身近なものでは、スポーツ教室やグランドゴルフ、近所の友人とのおしゃべりなどが時に救いになります。親しい友人が亡くなったりすると、急に寂しさが離れなくなるようです。高齢の男性の多くは仲間を作らず、孤独の方が多いです。女性のように感情を共有するための感情言語を持たないことも原因です。男性は元来理論的な言語が中心なので、仲間での感情の交流のためのおしゃべりは苦手なのです。男性は老年期を生きにくいものです。生物としての遺伝的体質かもしれません(今よくみられる自然災害などでも地域、友人から切り離されることは相当の苦痛をもたらします)。
そうした意味で、「デイサービス」などはよくできていると思います。初めに嫌う人も多いですが、慣れると安定します。親切に面倒をみてくれて、同年代の話し相手もいます。遊びもあり楽しめるようです。週2,3回の通所でも、かなり安定して満足感が高いようです。
不安とは少し離れた話題になりますが、新聞の広告を見ていると健康保持のための医薬品、食品などの広告が圧倒的に多いです。健康雑誌かと間違うほどです。社会のニーズを反映しているといえます。
日本は老人大国への道を着実に進んでいます。「死が近づく」その中を生きるための個人としての「老人の哲学」や「自分なりの生きる指針」がさらに必要なようです。それは同時に死生観と向き合うことが基本となります。死は日常の裏側に常に隠されているからです。