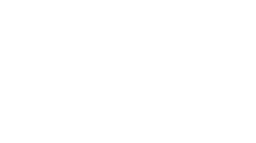2024年03月15日
不安について 第2章:不安とトラウマについて
不安は常にトラウマ(心の傷)と密接につながっています。不安とトラウマの関係をみてみましょう。
軽いものでは病院での注射の痛みなどの経験からトラウマが生じたりします、そのトラウマが予期不安を生みます。次の注射の時、トラウマの記憶から強い不安と恐怖が生じます。パニック状態で注射から逃げようと暴れたりします。症状が長引くのは、学童期の学校でのいじめの体験、事故や災害での死の恐怖、子供の死や親の病気などはその代表的な例です。時間が経ってもトラウマからの不安、恐怖のイメージが消えることはありません。
トラウマによる不安は、症状の軽いものから重症なものまでかなり幅があります。症状が重症になるのは、会社でのパワハラや学校でのいじめなど、対人関係での侵襲的な「対人恐怖」を起こすトラウマが特に強い場合です。この際には、場所を離れた自宅に戻っても、強いトラウマによる不安、恐怖が長引き、「対人恐怖」として持続し、後の人生まで影響を及ぼします。場所は限定されず、トラウマの発する恐怖、不安が長く人生を支配するのです。
そのためにその後の人生で社会への適応に苦労します。二次的に人生そのものに影響が広がるのです。
また特に重症なものとして、「幼児期の家庭生活」や「学童期のいじめなどの成長期」のトラウマの恐怖、不安は潜在的に持続します。長じて大学での生活や社会人になったときに、外部からの軽い刺激に対して強い反応を起こしやすくなります。大学では引きこもりなどが発生しやすく、社会人では、不適応や対人関係での疲れやすさ、抑うつ、不安を作る場合が多くみられます。結果的に長期の休養や退職などにつながります。
現在の仕事や環境そのものが直接の原因なのではなく、幼児期、学童期などからのトラウマが持続して、刺激に対して過剰に反応している状態といえます。
「反復性うつ病性障害」という病気がありますが、これは人生で何度もうつ病的発症を繰り返す病気です。こうした病気は昔のトラウマによる不安が影響している可能性が高いと思っています。
その他、形は様々です。離婚などの場合にもトラウマの影響がみられます。夫からのDVが原因とされ、離婚に至る場合は多くみられますが、時に妻の側に幼児期からのトラウマがあり、それが夫の態度に過剰に反応して、夫への不安、恐怖に広がり、別居して離婚の訴訟となる場合もあります。実際に夫のDVの場合も多いので、詳細に調べる必要がありますが、現実にはそうした動きは少ないようです。子供に離婚の悲劇が生まれないためにも、夫婦の関係やそれぞれの言い分のみならず、子供と夫との関係性もよく調べる必要があると思います(面会権に影響します)。
また、幅はありますが、トラウマは抑うつや適応の障害時に「自責の念」を生じやすくなります。さらに頭をたたかれたような過敏な反応が生じ、生きる意欲の喪失へとつながり、自傷行為や自殺に進みやすくなります。
さらに、対人恐怖を生じさせるパワハラやいじめが原因のトラウマの場合、そのトラウマの影響が広がり、「人酔い」のように人間集団への恐怖が強まり、店や駅、人混みなど、人の集まる場所に行くことに対して強く不安が生じます。集団からの視線や人混みに圧迫され、怖いのです。
さらに不安が進むと、外出への恐怖症になります。家に引きこもり、外に出ることにおびえ、疲れを感じ、家に引きこもるようになります。
パワハラなど心的外傷においてみられる特徴の一つに、心的外傷の対象に近づくことに対して、最初に強い不安が生じ、警告が発せられることがあります。さらに対象に近づくと緊張、興奮、恐怖などの強いマイナスの感情が出現し、神経が異常に高ぶります。この時、さらに危険を再現するフラッシュバックからの強い恐怖が生じます
この高ぶりのレベルは相当なものです。薬の量に換算すると、神経の高ぶりを止めるために通常の6倍から10倍もの強さの薬が必要になります。しかし、うまく対象から離れるか、避けられると、薬が必要なくなるほど不思議なぐらい急激に神経は安定します。
また、不安はあらゆる精神障害に合併します。不安障害、心的外傷後遺障害、強迫性障害、うつ病、統合失調症、ストレス反応、適応障害、自律神経失調症、人格障害などです、実際不安を伴わない疾患はないとさえいえます。不安は様々な症状の普遍的な基盤を形成しているといえます。精神の不調という恐怖の生じる事態に反応しているといえます。
人間関係でのトラウマにみられるのは、時に「死を連想させる恐怖」であり、さらに二次的には、「集団から疎外されることへの恐怖」につながります。社会の中では集団への適応こそ一番大事と教えられてきます。集団から疎外されることは、心の深層で「社会的死」を連想させる強い恐怖であり、不安の生じる基本にあると思われます。
次に、こうした不安発作などに発展しやすい不安とは別に、日常的に環境の中で発生している不安があります。生きていることの実存的な不安であり、まさにハイデッガーの世界です。次の章で述べます。