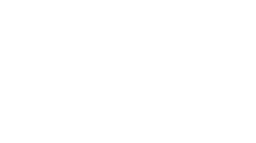ブログ
2024年03月15日
フッサールの現象学の問題について
この章は大変難しいと思われる内容です。精神科の精神病理学という私の専攻分野の話です。
読み飛ばしてもらって結構です。ただ、「精神科医とはこんなことを考えているのか」と参考程度にみてもらってもいいかと思います。
今回の問題の始まりは、主観と客観の整合性の問題です(西洋哲学ではデカルトやカントのテーマに類似します。さらにはプラトン的二元論かアリストテレスの一元論かという話に戻るところがあります。ただカントの結論では客観的認識は存在しないとされています)。
現象学について少し説明します。
「今、目の前にあるリンゴが本当に実在するのか、自分の想像の産物でしかないのか。」さらには、本当に実在していると仮定して、正確にその姿を真に認識できているのかという問題です。実際どっちでもいいような話なのですが、重要な意味があるのです。
目の前に患者さんがいるとします。その姿や症状、言葉を記録して、論文で発表したとします。最初に問われることの一つに、「そのように自分の見たものや感じたことを文章で表現するけれども、その自分の認識が本当に正確に客観性があると断言してもいいのか」という問題です。
見えているものは自分の思い込みに過ぎない偏見かもしれません。自分の思い込みであればその論文は学問としては客観的に正当性があるとは言えなくなります。ですから客観性がある論文といえる保証としての正当な根拠が必要なのです。
この正当性に関しては混乱を生じやすい議論です。ただ疑いだせば、精神科の記述病理的論文の客観的信用性が失われてしまう重要な問題なのです。
そこにフッサールの登場する意味があります。
彼はカントを現象学という学問の始祖にして、独自に上記の問題を解決する方法を提示します。簡単に言えば
「先入観や思考を停止(エポケー)することは、人間の内面に現れる、あるがままの「事象そのもの」へ接近する手法であり、主観を排除することで、直観という認識の根源の機能が働き、思考の停止の中で見えてくるものは客観的、普遍的妥当性がある。」と論じました。
また、「根拠の基本は自分の感覚から得られる直感であり、感覚は普遍性を持っているからそこから得られるものは客観的であるといえる。」と論じます。
(精神科の代表的な古典であるヤスパースの精神病理学序説でもエポケーという方法が使われていますが、フッサールとは少し違うようです。)
フッサールは1859年モラビア(チェコ共和国東部の地方)生まれ、1938年に没しています。
彼の研究はナチスに敵視され、論文の多くも離散し、第二次世界大戦後に少しずつ発見されました。しかし、大量の著作があり、今でも復刊が続いているようですがまだ全体として未完のままです。
日本では、ドイツに留学していた木村敏(きむら びん)氏が中心となり、ドイツでもブランケンブルグなどがフッサールの研究を進めました。木村氏は日本に帰り、笠原嘉(かさはら よみし)氏などと共同研究を進め、日本でのフッサール現象学を確立しました。彼はその後京都大学の教授となり、日本の精神科の権威として尊敬されてきました。
当時から、現象学の世界での最大のテーマは「物」が対象ではなく「現象学的手法で他者を理解できるのか」という他者認識に関する根源的な問題にありました。ただ、確かなことはフッサールの書籍からの解析は事物や地平線の領域までは進んでいましたが、目の前にいる人間の認識、つまり他者の認識まではまだ進んでいませんでした。
フッサール自身も、またその後継者もこの問題の解決に悩んでいたようです。
こうした現象学の他者認識の限界点は木村氏の中で意識されていたのでしょうか。
実際、他者の存在を扱うのが精神科の論文だからです。
その点に関して難しいですが、要約すれば木村氏は独自に現象学を打ち立てました。彼によれば「人は生命一般の根拠として生命同士のあいだに絶えず密接な関係、『あいだ』を持ち続け、人が出会うとそれが保持され、意識の中に表象として現れ、認識されていく。そしてこの表象は根拠とのつながりからはずれないように制御され標識として役に立つ」として、その『あいだ』の構造を明らかにしようとしました。さらに、「思考対象な主体が意識の表象の面で自己という表象と違うものが自己ならざるもの、他者として区別され、自己が確立されていく、そして自己ならざる者との生命の根拠の認識としての『あいだ』があれば他者を認識することができる」という彼独自の「フッサール流の現象学的立場」からの説明を確立しました。
彼の理論はこの「あいだ」の説明と解釈が中心であったといえます。
他の精神病理学医も彼から学び、現象学的「エポケー」をすることで、他者を理解することは客観性があると保証されている行為と判断されていました。ここでは自己と他者の問題は乗り越えられていたのです。私もそれを確かめるためにフッサールの著書「イデーン」の日本語訳から勉強しなおしたのですが、フッサールの翻訳版の原文は実に読みにくい、難解な文章でした。なかなか進みません。フッサール自身の苦行を物語るようです。
そこで、理解のために現象学の哲学者としてフッサールの研究の第一人者である谷徹(たに とおる)氏の解説本を読んでみました。すると、フッサールの世界の特徴や、フッサールにおいて他者認識の困難さが解決されていないことについて述べられていました。
すると、日本の現象学的他者理解と矛盾します。本当に木村氏の方法で他者理解という難問が解決したのでしょうか。
その問いの答えにちょうど役に立つ興味深い本があります。
木村氏著作の「あいだ」という短い文庫本です。木村敏氏が著作し、奇遇にも友人である谷徹氏に解説を依頼した本なのです。
解説を読むと、谷徹氏の解説は多少辛辣なものでした。
木村敏氏の思想や個人の主体性の確立が、生命の根拠の「おのずから」に呼応して間主体的(かんしゅたいてき)な世界を構成しているということに強く共鳴しながらも、内容の現象学的側面には触れず、木村氏の理論は、むしろ解釈学の範疇ではないかと本音をやわらかく語っています。
ここで解釈学に触れますが、これは、聖書などのように絶対的テキストの原点が最初にあり、その内容の理解の仕方を研究する学問で、デイルタイ、ガダマーなどが代表です。
この解釈学は、存在そのものを問う現象学とは全く相容れない学問なのです。
最初に確立された教義があり、それを解説、理解を深めるための学問です。
つまり、谷徹氏は、木村敏氏の「あいだ」という理解は、先に教義のように「あいだ」という実在がありその解説をしている、解釈学的な書物であり、さらに言えば非現象学的な書物であると暗に述べているのです。
実際、翻訳の進んだフッサールの晩年の思索は、他者理解の困難さから、認識に至る原風景の再確認という事物の存在の垂直的深度の方向へ移動していたようです。
谷徹氏の意見が正しいとすると、木村敏氏に倣い、エポケーを採用することで現象学的理解に達することができると信じて、現象学的手法で描かれたと述べられている多くの論文は、実は現象学的でない、他者の客観的理解の根拠がないことになります。
これは大きな問題があります。私の手に余る問題であると考えています。
ぜひ「あいだ」という本の内容と解説を見比べてみてください。
木村敏氏同様、現象学的手法で症例アンネ・ラウについての「自明性の喪失」を描いたブランケンブルグ氏も以前来日したので、講演を聞いたことがありますが、彼は症例アンネに触れられたくない、むしろ若気の至りの書物であるというようなことを言外に臭わせていました。
症状の記述の現象学的方法に関しては難しい問題が残されているようです。