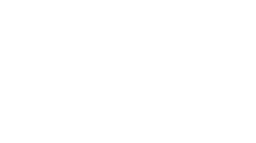1.診断書などにおいて診断名を「うつ病」ではなく「うつ状態」などと状態像で書くことが多いのです。すると診察室で患者さんから「うつ状態とうつ病は違うのですか?」とよく聞かれることがあります。
今回は診断名によく使われる「うつ状態」と「うつ病」の違いを中心に説明します。
診断の問題は難しいので長くなりますが、一般論から述べていきます。
まず、病名や状態像とは何でしょうか。
病名(疾患単位)とは本来、治療法や今後の見通し、原因や予後を含んだ統一性のある基準から成り立ちます。一方、状態像診断は、「表面に現れる症状のまとめ」です。現在ある多くの症状の中で、中心となる症状をまとめて簡潔に表現したものです。
現在の診断名はどのようにして決まるのでしょうか。通常、ICD10やDSM3などの「診断学の本」で決定される「診断名」を指します。この診断学の本の特徴は、「診断名」は主に、病気を特定の症状と、その持続期間から病名を選んで決定することにあります。病気の原因、経過には触れません。ICDにおける診断名とは、簡単に言えば「博物学的な」病気の分類学です。そのため、こうした本は「操作的診断」とか「分類的診断」とも呼ばれています。ただ、内容は普遍的なので、世界的な区域での病名の統一や、研究の標準化に大きく貢献しました。
しかし、ICDなどの診断学の問題は、古典的にすでに基準のある病名(うつ病、統合失調症、躁うつ病、発達障害、人格障害など)と、症状をとらえるのみの「状態像」による診断名(不安性障害、強迫性障害、適応障害、重症ストレス障害など)が同列に混在していることです。
現在の診断学では、例えば、「不安」を呈する一定の症状が中心にあれば、「不安性障害」であり、会社や学校に行けなければ、ストレス反応としての「適応障害」と診断されます(ただ、この適応障害もストレス性の原因に基づくのですが、しかも6か月という使用期間があるので、期間を過ぎれば変更する必要があります)。
ICD診断名の選択は簡単ですが、診断名が治療上大事なのは症状を引き起こす原因、経過にあるといえます。「操作的診断」には、上記のように、単に現在の症状をまとめて確認し追認するだけの病名があります。
その意味では、先ほど述べたようにこうした病名は予後や見通しのしっかりした独立した病名としてとらえるよりも症状をまとめた「状態像」診断と考えていいと思います。
「状態像診断」の何が問題でしょうか。これは内科でも同様の場合が多くあります。
「学校に行けない」と訴えて内科を受診すれば、「起立性調節性障害」と診断されます(精神科的には自律神経失調症の一種かと思います)。
起床時、血圧が低いこと、覚醒度が低いことを意味するのですが、家族はその身体的病気が原因で学校に行けないと考えてしまいます。これは、明らかに順番が逆で、「何らかの原因で学校に行けなくなる」→「結果的に本人も焦りや苦しさがあるので、二次的に自律神経のバランスが崩れる」→「その症状が起立性低血圧」で、不登校の原因ではなく、結果としての症状と考えるべきなのです。
同じように、実際に学校に行けない場合、精神科では「適応障害」と診断される場合が多いです。実際は「何が不登校の原因か」が問題になるでしょうが、「適応障害」という病名のみでは、受け取り方によっては本人の素因に何らかの責任があるようにも聞こえてしまいます。また、適応障害もその定義は「ストレス障害の結果の症状」なのですから、治療上、「ストレス原因そのものの解明」がさらに必要になります。
学校に行けない場合、原因は、友人からのいじめ、仲間外れ、親の過干渉、あるいは無関心家庭内での対立、本人の過敏性、勉強の重圧、対人恐怖、思春期の自意識過剰など理由は多岐にわたります。適応障害という病名では原因の説明になりません。また、今後の予後の見通しや治療法を示すものでもありません。やはりこれは表面的な「状態像」による診断名と考えるべきです。
さらに、問題を深めると、通常の診断の際にも混乱があります。実際の臨床での症状は状態が複合している場合が多いことが関係します。
例えば、職場での出社不能、出社恐怖、出社拒否を考えてみます。
職場で、やや人付き合いが苦手の人が、仲間から孤立したり、疲れやすくオーバーワークで疲弊したり、上司からパワハラ的な冷たい態度をとられるなど複合的要素があると、不眠、不安、恐怖、抑うつ、トラウマ、パニック発作、動悸、頭痛、腹痛などの多彩な症状を呈する場合が多くあります。
症状が多彩であれば、主症状が問題になりますが、症状からは不眠症、不安性障害、適応障害、自律神経失調症、心的外傷障害、転換性障害、人格障害などの多くの状態像の病名が当てはまります。
どれか一つに決めることが困難な場合が実は多いのです。
ここで問題をまとめると人間の精神には原因、過去からの経過などの複雑さがあり適当な診断基準を満たさない症状の方や症状が多岐にわたる場合の方が多いということです。
以前のDSMではそうした欠点を是正するために、症状のみならず多軸診断という形で、性格傾向や個人の歴史を加味して、総合的に病名を診断する方法を採用していたのですが、煩雑になりあまり使われなくなったようです。
ですから、患者さんの側では診断名にあまりこだわらず、何が起こっているのか、原因や予後を含めて総合的に理解、把握することがすること、さらにはそうした説明が実は診断名より大事なのです。
次に、診断名があまり有効でない、あるいは、原因や経過に関して調べる必要がある場合です。
仮の診断として原因をつけた状態像診断という形を利用したほうがわかりやすい場合があります「いじめが原因の適応障害」「不安定な家庭環境による適応障害」「過敏性の高いことによる適応障害」など、原因を付加するだけでもだいぶイメージができます。
ICDやDSMの診断学の出る以前の診断(約30年前)では、「状態像診断」という診断がよくありました。
これは、精神の状態を見てそのまま記載するやり方です。当時から状態像診断は「主に病名診断にうまく分類できない」あるいは「適当な病名を選ぶことが難しい場合や、多岐にわたる精神状態がみられる」などで診断が確定できない場合などによく使われました。状態像診断は病名よりも幅が広く、むしろ病状がわかりやすいので使いやすいものもありました。
例えば、昔はうつ病を区別して「荷下ろしうつ病」とか「神経症性うつ病」「境界型うつ病」「慢性疲労性うつ病」などの原因を含めて診断したものです。
うつ状態という言葉もこの頃のものです。ICDの診断にはうつ状態という言葉はありません。
2.上記を参考に、ここで本題に戻り、なぜ「うつ病」ではなく「うつ状態」と状態像で病名を記載するのでしょうか。「うつ」という言葉の多様性を含めて、もう一度見直しておく必要がある問題なのです。
「うつ」という言葉の中には、程度の差はあれ、気分の落ち込み、憂鬱感、意欲の低下などの症状が含まれます。「うつ」という言葉には病名としての「うつ病」の意味と「抑うつ的症状」を呈しているという二つの意味が含まれています。しかもこのうつ症状は、不安性障害や強迫性障害、統合失調症、心的外傷後遺障害などあらゆる疾患に合併します。うつ症状の見られない精神疾患はほとんどないといえます。
ですから、「うつ状態」という言葉による診断にはとりあえず、「うつの状態を改善し、それから原因となる病気の治療を考えましょう」という意味合いが強い診断名なのです。
一方うつ病は「固定した」病気です。
「うつ病」という診断の場合、基本的にこれは脳の神経の病気(原因不明のセロトニンの減少)を指します。病気として改善には一定の時間を要し、一連の症状の経過があり、薬物療法などが必ず必要になります。治るまで数週間から数か月、時に半年を要します。治りがけの希死念慮、自殺企図に注意しろとよく言われたものです。
うつ病は神経の病気ですから一定の症状、経過、予後が必ず見られました(最近うつ病の軽症化が叫ばれています。実際軽症化しているといえますが、本当のうつ病そのものかは問題です)。
「うつ状態」の場合を見てみましょう。
例えば家族の死、交通事故、経済的損失、恋人との別れ、過労、パワハラ、対立など様々なストレス、将来への不安などの負荷があると、だれでも意欲が低下し、気分も「抑うつ的」になります。この場合、原因は割とはっきり存在していて、しかも症状としてうつの症状が強くみられるのです。おそらくセロトニンの分泌が圧迫されている状況といえます。ただ、原因が解決すれば改善する可能性の高い「うつの状態」です。定型的な「うつ病」の自然経過とは異なります。うつ状態は、例えば「会社などで休職すると途端に一時改善するが、また複職すると再燃する」など、状況に依存している場合もみられます。これは心的外傷の場合に多く見られます。
抑うつ症状にも少量の抗うつ剤はよく利きます。この場合ストレスでおそらく神経が圧迫されていると考えるのが妥当です。
(また、先ほど述べたように「抑うつ症状」はほかにも不安性障害や心的外傷、強迫症、慢性疲労などにも他の精神疾患にも合併します。うつ症状と抑うつ症状は意味は同じです。文脈でうつを強調したいときに抑うつ症状と記載する場合が多いようです。およそ精神疾患で「うつの症状」を合併しない精神疾患はほとんどないといってもよいと思います。)
実際 抑うつ症状は幅が広いのです。
結果的に、診断書で細かい診断が難しい場合、あるいは診断名がうまく当てはまらない場合なども「うつ状態」という仮の診断名として活用し、経過や原因、様子をこれから見ていく場合が多いです。私は時にカッコ付で(慢性疲労)(心的外傷)(不安性障害)などと原因などを補充して診断名をつける場合が多いです。
また、実際には職場ではオーバーワークか、パワハラ類似のものによるうつ状態が原因のほとんどですが、そうしたことはあまり診断名にかけません。せいぜい慢性疲労などとカッコに入れるぐらいです。
ただ、繰り返しになりますが方針としてはうつの症状を改善しながら、問題を明確にして改善していくということです。
このように、定型的うつ病と分けて「抑うつ症状」が中心の病状を「うつ状態」と呼んでいるのです。時に「うつ病」か「うつ状態」か明確な判断は難しい場合もあります。確かにうつ状態の中に本当のうつ病の患者が入っている可能性はありますが、その時点で再度判断すればよいのです。
「うつ状態」も症状は表面的にうつ病に似ています。不眠、食欲の低下、抑うつ気分、意欲低下などがみられます。
「うつ状態」はストレス性の疾患が原因の場合が多いので、ストレス原因の場所や人と離れ、ゆっくりした休養が大事です。会社での過労が原因であれば休職して休むことが大事です。また、パワハラでも会社を休んでトラブルの相手と顔を合わせないことも大事です。
家で休み、原因から離れれば、家では短期間で次第に体調もよく元気になれます。
気分転換の活動も必要です。
これは、家で長期間、休養中でも絶対安静の必要なうつ病の症状との違いです。
(ただし、「うつ状態」でも性格や原因によって症状が長引く場合も多いです。)
ただ、「うつ状態」は家では改善しても、会社に近づくと悪化する(自律神経の症状が多いです)傾向が強くみられます(トラウマと似ています)。
そのため、ストレス源の何らかの改善と、休養の延長が必要な場合が多いといえます。
「うつ状態」は、気分転換、考え方、休養や、リハビリが大事です。それが治療方針になります。
「うつ病」は安静と薬物療法です。無理をしないで、一定期間の絶対的休養とその後の少しずつのリハビリが必要になります。
ちなみに古典的な状態像診断には、ほかに、朦朧状態、錯乱状態、解離状態、幻覚妄想状態などの診断があります。
この場合、病気の原因がはっきりせず、診断が確定できないため、時間をかけて診断をつけていく前段階という意味合いが強いとも言えます。
確定した病名に達する情報の無い場合の仮の診断の場合もあります。
長くなりましたが、元に戻して、「うつ状態」と「うつ病」の病名の違い、治療の違いが多少わかっていただけると幸いです。