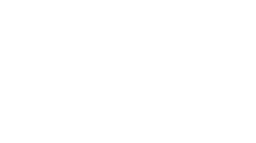2023年10月18日
HSPについて 第1章:Highly Sensitive Parson―過敏な人 総論
HSPという言葉を知っている、あるいは聞いたことがある方は特に女性において非常に多いと思います。外来でもよく質問されるし、こちら側(私の側)で使用してもほとんどの方がその言葉を知っています。自分は「HSP」であるといわれる方も非常に多いです。しかし逆に「過敏な人」というイメージ以上に具体的にその概念や病因に関して、ある程度の知識のある人は圧倒的に少ないといえます。
HSPの概念はアメリカの心理学者エレインアーロンの観察、治療から導かれたある意味であいまいさの強い用語です。ですから世間的に病気なのか、体質なのか性格の傾向、特徴なのかと混乱をきたしやすいといえます、また用語そのものが異常と正常の差がつきにくい幅の広い概念であるため医学の領域ではそれほど研究の対象になってきませんでした。
このブログではHSPに関して、医学の領域から何回かのシリーズに分けて考察し、よりHSPの概念を深め、検証を進めたいと思います。
初めに心理学の領域から問題を成書から整理しましょう。
そこではHSPに関する定義,成因、病気そのものに混乱があります。
以下のA.Bの二つです。
A、HSPの原因として、発達障害(自閉症スペクトラム障害)に基づく体質的な病的過敏性の概念と、さらに性格、成育歴や環境因が原因と思われる一般的な過敏性概念の2種類の概念が混同されていること。
B、後者のように環境因や成育歴をHSPの原因であるという立場に立つて考えるとき、その原因となる成育歴、環境因に大きな異常や特徴が見出しにくいことが挙げられます。これまで母子関係を中心とする家庭環境を原因とする子供の症状には愛着障害や複雑性PTSD、機能不全家族という概念があります。しかしこれらは、離別や虐待などの強い負因が中心で。症状も重くHSPであるという訴えは少ないといえます。実際に外来で見かけるHSPを訴える人にはそれほど大きな母子関係。家庭環境のひずみが見出せない場合が多いことです。
またさらには、素因と呼ぶべき過敏性の体質を示す所見はありません。
この問題を整理しながら、なぜ圧倒的に多くの人がHSPという言葉を使い、用語が広がるのか再検討が必要になります。
数字や画像に出ない問題を考察、検討するとき。必要なものは臨床的患者さんの情報の整理です。そうした情報の整理から一定の結論を導き出す研究はナラティブ的手法と呼ばれます。
ここでは、ナラティブな手法でHSPの問題を再整理し、どのようにとらえるべきか考察し同時にHSPの人の治療的自己対応についても考えてみることにします。
まず、HSPの人(過敏性の高い人)の自らのべる一般的特徴について長くなりますが列挙してあげておきます。
・人の顔色が常に気になる
・人と話すことに気を遣う
・怒らせるのが怖い
・人から嫌われたくない
・対人関係の不安を克服できない
・人の態度に過敏に反応してしまう
・自分の意思がわからない
・コミュニケーションで緊張する
・他人への対応で反省会をしてしまう
・何のために生きているのかわからない
・自分が悪いとせめてしまう
・NOといえない
・人と会うと疲れてしまうなどです
こうした症状は、大変多くの人が訴えますが、確かに過敏性と呼ぶ以外に特定の病気の特徴を示さない非特異的症状です。
ここで先ずHSPという概念を混乱させるAの理由を成書で考えてみます。
非特異的症状のために、過敏性という言葉で「発達障害の体質的過敏性」と「環境因由来の過敏性」の両者が混同されています。しかし細かくみると両者は社会性や過敏性の質に大きな差があります。発達障害は「空気の読めない人たち」であり、非社会的な自閉症スペクトラムとしての「知覚の過敏性」を有します、一方「空気を読みすぎる」環境因由来の人たちは、対人関係に気を使い、「対人過緊張に基づく過敏性」がみられます。社会性に気を使いすぎる過敏性です。両者は同じように過敏性と呼ばれても、ともに全く異なる種類の病気と理解してください。
HSP概念の最初の提唱者であるアメリカの心理学者のエレインアーロンの本の中でも両者が混同されています。ただ詳しくみると彼女の提唱したHSPの概念は発達障害寄りであるといえます。一方日本の研究者は概念が環境因寄りと言えます。これは国民性、患者さんの量の差が関係しているかもしれません。
発達障害による過敏性はHSPではなく、発達障害の随伴症状としての過敏性と分類理解されるべきです。
過敏症状をもう一度まとめ分類すると以下のように分けられます。
① 光や音に過敏(知覚の過敏)
② 社会的な対人関係での過敏(環境因の過敏さ)
この二つの過敏性の中で1の要素が中心であれば自閉症スペクトラム、発達障害。2が中心であればHSPに近いとおおざっぱにですが分類することが可能であるといえます。
次に、大きな問題となる環境因Bとはいったいどのような環境なのでしょうか?