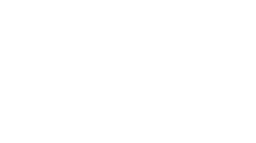2023年10月18日
HSPについて 第2章:HSPとは何か、HSPの理解
家庭の環境因に関して医学的には母子関係の障害であるボウルビィの「愛着障害」の概念、さらに最近では、機能不全家族などが代表として挙げられます。
しかしその場合の環境因は機能不全家庭のように強い愛着の障害、愛情の欠損を起こす離別や暴力、虐待などの過酷な家庭崩壊が基本にあるといえます。その場合解離性障害や人格障害の病名が示す如く強い症状を呈します。
そうした厳しい環境を原因とする人とは別に通常に見える家庭環境の中でHSPと自覚する人の中が外来に多くいます。
HSPを理解するにはむしろ正常に見える通常の家庭の中をさらに注意して見てみることになります。
特に臨床の現場で得られる外来の多くの患者さんの例は、家庭内での原因の問題をもっと別な視点から考えることの必要性を教えてくれます。
また、家庭環境の問題を家庭の面から考えると特に特異性はありません。
そこで、患者さんの特徴から定義を考える必要があります。
通常過敏性だけを主訴に外来受診する患者さんは少ないです。病名としてうつ状態、不安症、適応障害。慢性疲労。自律神経失調症、など多彩な症状や病名で受診する外来の多くの患者さんたちの中から過敏性の自覚。家族構成やその関係性。自己理解を確認するとHSP的過敏性の症状の自覚して訴える人が非常に多く、さらに大事な点は彼らには家庭内での過剰適応という共通点があります。
この共通点とは何でしょうか。
結論的にはHSPの最大の問題は、幼少期から続いている「通常に近い、しかし多少ひずみのあるささいな家庭環境因への本来正常な過剰「適応」が、逆に将来、過敏性という形で社会への不適応をつくるという「パラドックス」にあることが見えてきます。適応と凝縮。均一性を求める日本社会の圧力が家庭内にも無言の影響を及ぼしているともいえると思います。
そこで次に家庭内適応のテーマに関して考えてみます。育った家庭の環境の問題が基本ですが、機能不全家族などの言葉にみられる激しい家庭内の対立や暴力、依存症や育児放棄や虐待などの外からも見える家庭内のトラブルほど大きな問題はありません。日常的に問題ないと思われる通常の普通の家庭の中に潜む小さな問題が大きな意味を持つのです。
機能不全家族とは時に程度の差かもしれませんが、そこでは常に幼児期の家族内の通常にある人間関係が問題になります。共通するのは、家の中に祖母と母親の間、両親の間などに些細な対立や軽い争いがあることです。さらには少数ですが強い父親の態度や母親の強制など服従の種があることです。
家庭内で通常的にもよく見られる当たり前に近い軽いひずみや対立のある時、子供はどのように家庭に適応するのでしょうか?
その場合ほとんどすべての子供、特に女の子は、家庭。居場所を大事にしようと考えます。動物としての子供の本能に導かれるように家の中で対立を解消するために両者に気を使います。程度の差はあれ、自分のためではなく家庭の環境を良くしようと努力します。その際「手のかからないいい子」「家の中で明るい種を作るために勉強や習い事で努力する」「明るい話題」「対立するどちらにももめないように気を遣う」などの役割を演じます。結局「家庭を壊したくない、親の期待を裏切りたくない」のです。
自分のわがままや言い分は我慢し、不満や甘えは抑圧されます。自己の意見を失うのです。
こうした状況は、一見どこにでもある風景で病的な印象でないかもしれません。そうした自我の特徴を表す病名もありません。しかし、その我慢の程度が強いと成長して大人になっても学校や職場でも家庭での役割と同じく周囲に気を遣う役割を無意識に常に演じて無理をしてしまいます。「NO」といえない、生きにくいつらさがあります。結局常に人に気を遣う、緊張間の高いHSPとして行動してしまうのです。
この際同時に自我の未熟さがみられます。人格の形成の幼児期から人に気づかいしすぎることで自然な自我の成長が妨げられてしまいます。幼児性とトラブルに対しての脆弱性が見られます。強く反応してしまうのです。機能不全家族にみられる、人格障害などの重症の障害ではありませんが、軽いひずみがあります。
また、自我意識として共通に「自分はダメな人間だ」「役に立たない子供だ」と家庭内で(家庭を守る生物としての本能に導かれるように)自分を過小評価して暗い気分に襲われます。
可愛がられ、甘えたり、わがままを言ったりする成育過程から得られる自我の自然な成長や自己肯定感を妨げられます。自分の努力にもかかわらず、育った家庭内は変化しないので、自己否定の感覚が強くなるのかもしれません。この感覚はあたかも動物的な本能の強制であるかのように子供自身を強く束縛します。言葉を変えれば作られた超自我による強い支配があるとも言えます。自分らしさ、自分の居場所は失われ、人目を気にしながら生きる窮屈なつらい人生が始まります。
自己の過小評価の程度が強いと。いわゆる「リストカット」などの自分を責め傷つける自傷行為などが発生します。切ることで安心するのです。自分を追い詰めて圧迫から解放されるといえます。これはヒステリー的に人に訴えるためではありません。
逆に、「リストカット」を見たら、幼児期からの軽い不安定な家庭、(時には機能不全家族とよばれるような機能を消失した家庭)で無理を重ねて適応してきたと判断してほぼ間違いありません。
以上まとめると
HSPにはその結果二つの大きな特徴、共通点が生まれます
1,対人関係に気を遣う。相手の機嫌を損なわないように努力する
2,自己評価が低い
1の特徴が学校や職場でも続き。対人関係に気を使い、人の機嫌を損ねないようにNOと言えない自分が生じること。また怒鳴り声や対立におびえ過敏で常に周囲に気を使っています。そうした自分に疲れています。
幼児期からの自分の家庭内での適応性を同じように、学校や会社で繰り返して気を使いかえって不適応を起こしている状態にあるという理解です。
HSPの人は非常に素直な、いい人で。仕事にも努力します。しかし、結局無理を重ねて体調を悪くする人や人間関係でいじめ、過剰な気遣いや、対立に弱く、緊張感が強く疲れてしまう人などが多くみられます。
2の特徴もほぼ全員にみられます。ある意味で甘えてわがままに育てず、家族のために無理して適応して生きているので、親や他人から認められる、褒められる機会が少ないこと、また、結局自分が努力しても家族の関係が変わらないため「自分は役に立たない子供だ」「生きている資格がない」と強い自責感、うつが生まれ、時に悪化すると自傷行為(リストカット)が生じます。
こうした共通して認められる特徴の理由を考えると、「子供の本能」という理屈を超えた生物としての基本に由来しているからと考えるのが正しいと思います。
重なりますが、HSPの診断は比較的容易で
◎自覚症状として、生きにくさや疲れを感じる、対人関係に非常に気を遣う、うつになりやすい、生きる意味が分からない、苦しいほど完全壁、怒鳴り声や人の争いが怖い など
◎自分を責めやすい、常に自分が悪いと自責感にかられる
◎人に認められるために無理な行動をしやすい
などの自己分析です。
HSPのどこからが病的であるかは、本人の生きにくさと周りの気遣いの程度で決まります。
重症化してクリニックに来るときは、大まかにはトラウマ、オーバーワーク、うつ状態などの問題で来院されます。
そうした治療については3章に移ります。