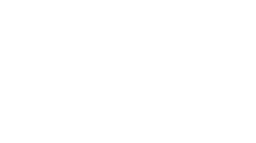2023年10月18日
HSPについて 第3章:治療の考え方、その他、重症化としてのトラウマ
症状のレベルで軽いものから重度まで大きな幅があり、対応にも開きがあります。
ただ、基本的にはHSPとしてのそうした自分の生きにくさの真の原因を知ること、自己理解が第一です。家族の中で気を使いすぎてきたこと、その行動様式や価値観をその後学校や社会で繰り返してしまっていることへの自己理解が必要です。
なぜ同じ対応繰り返し続けるのでしょうか。
この時、自分を支配する自分、成育環境のなかで作られた自分、いわゆる超自我の存在に気づくことです。
その問題を考える前に話がずれますがここで先に一度薬の役割を述べておきます。
治療で薬を使うのは、症状を和らげて、脳の過剰な負担を軽減するためです。HSPの人は不安、不眠、意欲の低下、抑うつ気分、イライラなどの症状が生じやすいのです。
症状とは感情や気分が不安定になっていることだと理解してください。薬が感情をコントロールします。
症状があると感情的になり脳の働きが悪く、ネガティブな判断をします。、どう考えても悪い結論になりがちです。薬で症状を和らげると、脳の働きがよくなり前向きの結論、思考がポジティブになります。判断や思考をするための準備のためと思ってください。
HSPの基本にある超自我の問題に戻ります。
私たちは通常、自分の自然な考え方が過剰に抑圧され、当たり前のごとく「気を使わねばならぬ」「こうしなければならない」という強い固定観念に支配されています。これは本当の自分ではなく、作られた別な自分、フロイトのいういわゆる超自我の強い支配が働いているからです。自我は「本当の自己」と環境でつくられた「超自我」の二つで自我で構成されています。
HSPの人は固定観念、超自我に強く支配され、常に超自我は自責や反省の念を強いてきます。
治療の基本はこの超自我からの脱出が大事なテーマとなります。
その一番基本的な方法は、まず自分の考え方に疑問、疑いを持つこと、これまで当たり前だと思っていることを疑うことにあります。超自我を抑え込もうと自分と戦ってはいけません。疲弊してしまうだけです。
「なぜそう考えるのか」とか疑問を持ち、固定観念の根拠を疑うことです。次に「本当にひつようなのか」「考えなくていいのでは」など自分との対話の中で少しずつ超自我に距離を置いていくことが必要になります。共存しながら距離を置くことで超自我から少しでも解放されると過剰な抑圧的考え方が減り、楽になっていくとおもってください。
超自我のコントロールは通常自分の生きる当然の原則や義務として頭の中に存在しています。ですから、超自我を否定することは自分を見失うように思われますが、抜け出すと自由な自分を見つけ出すので安定してきます。
超自我は頭の中にいるイメージです。頭の中が締め付けられるように支配されています。一方自分の自然な自我、(心とよんでもいいと思います)は胸に投影されているように感じられます。胸を意識してください。
HSPによる症状の重症化の場合を考えてみます。
HSPによる過敏性によるいろいろな体験が社会で拡張して人間関係の傷つきやすさから重症化するとトラウマや心的外傷に発展している場合があります。
トラウマそのものは人間の再度の危険を避けるための記憶装置であり、フラッシュバックなどの意志で超えられないおおきな後遺症状がみられます。
トラウマと直接戦うことは困難です。
その理由を脳の働きから考えてみましょう。
基本的な思考や理性の活動の部位は前頭葉で、ある程度自分の意志でコントロールできます。
しかしコントロールできない部分があります。側頭葉の活動です。
いやな記憶の再現やフラッシュバックなどの症状は両側頭(偏桃体の部位)から出ます。
前頭葉などの人間の意志のコントロール外の活動のためにそれを理性でコントロールできず、長く苦しみます。
治療薬を使用しますが、対応が難しいのです。ただフラッシュバックには一定のピークがあるので、自覚してピークが過ぎるまでやり過ごす構えが役に立ちます。戦わないことです。うまく共存する対応が必要です。
ただ根本的にはトラウマの源から遠ざかるか避けるしか方法はありません。
対象と会わないという安全保障が必要になります。
体調の管理も大切です。脳は体の臓器の一部です。過労や不眠などで機能が悪くなります。
不眠の改善などは最も重要です体調を改善してから考えることです。
さらに。脳の固定観念、超自我の機能を使うことを避け心の機能「やりたいことはやる、やりたくないことはしない」など素直な自分の感情に耳を傾ける必要があります。「気ままに考える」でいいのです。
少しずつ自己理解できると感情や思い込みに振り回されず、理性が働き、多少ブレーキを掛けられるようになります。
まとめると過去からの自分と現在の自分を分けていく作業であり、時にトラウマ(過去が現在に侵入する)そのものの治療と似てきます。
その後、症状に合わせて、「超自我」―作られた自分からのさらなる解放が必要です。
自分の中でも少し距離を置く工夫などです。束縛から解放される必要があります。
自分の感情が解放されるためには、やらねばならない。しなければならないことにこだわるのではなく。「寝たければねる、食べたければ食べる」気ままな姿勢が必要です。
また,正の感情―楽しい。ほっとする、気持ちがいい、おいしいなどの感情をなるべく多い行動をとることです。(認知行動療法的に)体調を整えて、脳の働きをポジティブにすることも大事です。
症状によりますが、薬の使用は補助的に体調を整え、疲れたネガティブな脳の働き、理性を回復するために使います。
(HSPの治療について追加)
HSPの人には、時に重症の場合もう一つの共通点があります。
幼児期の素直な親への甘え、健全な依存ができなかったため、正常な人格の成長が妨げられ、成人の自分の人格の中に、幼児期の自我が共存していることです。
時に、ストレスがあると、この幼児期の「自我」が、「怒れる自我」として別人格のように顔を出し、あたかも別な人格が出現したかのように態度が豹変し、急激な怒りが出たり、強い落ち込み、自傷行為などがみられます(人格障害と同じですが程度の違いはあります)。
つまり、幼児期の環境で、子供として甘えたい幼児の人格が、強い抑圧で成長できず、未成熟のまま残り、大人になってからの人格に統合されないまま、一部、別な人格として本人の人格の中に共存している状態です。普段は共存して隠れているのですが、刺激に対して、スイッチで切り替わるごとく前面に出現します。これが外的にはあたかも二重人格のごとくに見えます。
この抑圧された子供の自我を成長させることが、治療上大変重要になります。
方法は簡単でもあります。
本人の信頼できる恋人や友人に、あたかも3歳児が甘えるように喜ぶように接してもらうことです。
つまり、「膝枕してあげる」「頭をなでてあげる」「ハグしてあげる」などのスキンシップな対応です。言葉はあまりいりません。十分信頼し、甘えられて満足できる関係性が大事なのです。
そうして満足していく中で、子供の自我が「超自我」から解放され、真に成長して統合されていくのです。
調子の悪そうなときには、20代でも30代でもスキンシップを大事にしてください。