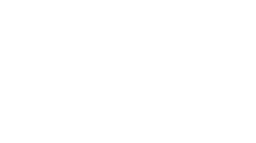2023年11月11日
心的外傷(トラウマ)と心的外傷後遺障害(PTSD)について 第1章:心的外傷(トラウマ)と心的外傷後遺障害(PTSD)について考える
心的外傷、トラウマの問題という言葉は日常的に使われる言葉になっています。
多くの方が言葉のイメージやだいたいの定義は理解されていると思います。
また、精神科の外来などでも、受診頻度が多く、時に一番難しい、時間を要する患者さんは心的外傷の患者さんともいえます。
このように、重要な病気、概念でありながら、外来でうつ病やパニック障害や不安性障害と比べても、診断などの医学的認知度が極めて低いという現実があります。
これはなぜでしょうか。
そうした疑問を踏まえつつ、少し踏み込んで心的外傷(トラウマ)の問題を考えていきたいと思います。
心的外傷の診断は、診断学上、現在の症状の確認が中心ですので比較的容易です。診断学の本であるICD-10を参考にします。
使われている言葉は難しいかもしれませんが、内容は平易です。
①無感覚と情動麻痺。他社からの孤立(直面すると動けなくなること)。
②周囲への鈍感、トラウマを想起させる活動や状況の回避(対象から逃げることです)。
③フラッシュバックなどの侵入的回想、悪夢(いやな場面を想起します)。
④原因として自然災害、激しい事故、変死、拷問、テロリズム、死の恐怖、犯罪の犠牲などの過酷な体験(原因の重度さです)。
⑤過敏性などの素因は診断に影響を与えないと考えます。
⑥元の原因を想起、思い起こされる体験をすると、恐怖やパニック、自律神経症状、驚愕、不眠、不安、抑うつの症状が発生する(合併する症状です)。
注目はこの④にあります。④の原因の項目の適応を除くと、上記の患者さんは外来でよく頻回にみられます。
心的外傷をめぐる混乱は昔からありました。つまり心的外傷後遺障害は、被害者が多くいて、しかも診断は容易であるのに、歴史的には混乱し続けてきた概念といえます。理由の一つは、精神医学の二大潮流である精神分析学において、フロイトがヒステリーとの鑑別上、心的外傷に否定的であったこと、また心的外傷という概念そのものがもう一方の潮流である精神病理学(統合失調症中心です)において全く研究対象ではなかったことが大きな原因です。
多くはヒステリーと診断され、心的外傷の概念は否定されてきたといえます。この壁を乗り越えるために多くの研究者は戦争などの極限の状態での病状の調査を行い、何とか近年認知されてきたというべきです。こうした歴史的重要な問題点はあとで述べます。
また別の問題があります。心的外傷の症状は自分の主観的体験が基準ですので、客観性に乏しい部分があり、時には心的外傷の範囲が拡大しやすい傾向があります。特に研究が、極限の精神状況を対象に進んできたことや、また、訴訟社会のアメリカでは精神障害としての心的外傷の範囲の拡大を防ぐことも大事で、新しい診断学のDSM-5などでも④の項目を強調してなるべく心的外傷の範囲を制限しようとしています。範囲を狭めようとするのは、誤診の減少という名目のためよりは、医療費、帰還兵の被害、訴訟対策などのいろいろな補償的、経済的出費を防ぐ理由があると考えてもいいと思われます。
こうしたことが、積極的に心的外傷の診断を行う精神的な壁になってきたといえるでしょう。
では、日本において心的外傷の現実はどうでしょうか。
実際に外来で多くの患者さんを診ていると、重症の方は当然として、軽症も含めて上記の心的外傷の症状で苦しんでいる多くの患者さんがいます。多くは④の解釈を除けば、他に項目に当てはまります。④を除けば、診断基準通りに心的外傷後遺症ととらえられ、しかもそうした判断、理解のもとで治療のできる多くの患者さんがいることに気づかされます。
ただ、症状が軽症の場合も多く、彼らは周辺群と呼ぶべきかもしれません。
時に心的外傷のトラウマから二次的に⑥のように不安発作などの症状へ広がる場合も多くみられます。一見、診断的に、不安障害やうつ状態、適応障害に分類される症状の人でもその病理の裏側に心的外傷体験の蓄積の多い方がたくさんいます。
これは問題となる④の症状の判断は何が大事でしょうか。恐怖や恥、傷つきには文化の差異はあると思います。特に日本社会のように、資質としてHSP的過敏性の高さが原因のトラウマや、仲間はずれなどでの、集団主義社会での傷つきの体験は、外見的には軽度に見えるけれども本人には予想より強い死や恐怖の体験となり、心的外傷の発生リスクを高めているといえます。死に近い体験や恐怖など④の現実的解釈には日本流の幅が必要といえるのです。④をどう理解するかが大きなカギであることをご理解ください。