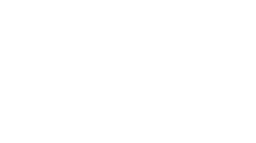2023年11月11日
心的外傷(トラウマ)と心的外傷後遺障害(PTSD)について 第2章:外来での症例について
まず典型例から見てみます。外来では、交通事故の後遺症、パワハラ、いじめ、暴言などの恐怖体験、時にオーバーワークの疲れ、仲間はずれなどに基づく後遺障害の方は大変多くいらっしゃいます。
そうした場合を症状として見ると、厳しい④の解釈以外の診断基準を十分満たしています。
現場や加害者の人間に近づくと、恐怖心で身がすくむ、また、吐き気、フラッシュバック、悪夢などの典型的な症状が発生し苦しみます。そして被害の現場に近づくことが全く困難になります。
これは心的外傷の中核群です。
また、その周辺に症状は軽症ではありますが、HSP的家庭内での対立、叱責、冗談、人間関係での孤立、離婚、些細な一言など、小さな問題が強い心的外傷体験、トラウマの原因になる場合が多くあります。それは後まで強い④以外のトラウマ体験として長引く場合が多いのです。
彼らは心的外傷、トラウマの恐怖の体験から、「また無視されたらどうしよう」「同じ失敗をしたらどうしよう」などと次の社会でも過度におびえています。また、実際に行動しようとしても体が動かなくなります。これは、個人の体質、過敏性の問題が強く影響しているかもしれません。しかし、そうした傷つきやすい、過敏体質の方にとって些細なトラウマが大きな恐怖を作り、周辺症状ともいうべき心的外傷体験の方が増えるのもまた日本の特徴かもしれません。
原因としてのトラウマの恐怖性は個人で大きな差があることの理解が必要です。
心的外傷の問題は症状の存在期間が長いことですが、ただその時に、その外傷の現場では苦しみますが、現場を離れると症状は改善する方が多いといえます。
ですから、「わざとではないか」と誤解されやすい方も多くみられます。
このテーマはあとで古典的に言われているヒステリーの問題で触れたいと思います。
さらに実例で場面ごとに具体例を整理してみましょう。
外来の患者さんでは、「職場で怒鳴られた」「厳しく言われた」など会社での恐怖の体験がトラウマを作る場合が一番多いです。
年齢や回数に限りません。怒鳴られた、注意された、などのショックがその後、強いトラウマとなり頭に焼き付きます。そして同じ場面や当該の人に出会うと恐怖のシーンが警報装置のように頭から吹き出し、フラッシュバック(恐怖の再現)が起こります。
恐怖とともにうつ気分、不安感や動悸、冷や汗、緊張などの自律神経の症状も見られます。
トラウマは頭の横側、感情の記憶である側頭葉の偏桃体の部分から発します。
前頭葉ではないため、理性でのコントロールが不可能です。
多分に、トラウマの記憶は人間を危機に陥らせないために危険を避け、警報を発する、HSPと同じように生物の本能に由来している大事な保護装置なのかもしれません。
会社での叱責、暴言による威嚇がトラウマとなり出社できない、出社してもその人に会うとフラッシュバックと恐怖で動けなくなります。
解決策は2つのみです。危険を避けるために配置転換で会わないようにするか、思い切って退職するか、あるいは上司当人が勤務場所を交代するかです。結局、絶対に遭遇しない安全保障が必要なのです。
これまでトラウマによる休職や、結果としての多くの退職、転職者を見てきました。
それ以外には、ほかには解決策、方法がない深刻な問題なのです。
パワハラは若年の被害者が多いようです。トラウマの加害者は中高年が多いのですが、彼らには悪意はないのかもしれません。ただ、自分の言葉、行動が相手にどういう影響を与えるか気づかないようです。中には常習的なパワハラの加害者がいる結果、その会社では常に若い人が辞めていき、慢性的な人手不足が続く職場も多くあります。これは会社にとっても存続の危機となる大きな損失です。経営者の方の強い自覚を促したいです。
ただ、この2、3年、パワハラ、トラウマに対する会社の対応が変わってきつつあります。
労働法の改革もあると思いますが、労災の適用やパワハラへの対応、職場復帰への支援など、以前にはない支援の工夫が見られます。5年前にはあり得なった光景かと思います。
政策が意味を持つことを初めて知りました。
「新型うつ」と呼ばれるうつ病があります。会社には行けないが、外では自由に行動できるうつ病の人を指すようです。これも会社でのトラウマがあり、心的外傷により職場には行けないけれども、家庭内や日常生活は可能、という心的外傷の例と考えたほうが理解しやすいと思います。これなどはうつの範疇でとらえるのではなく、心的外傷の視点から見ると不思議な話ではありません。
会社以外で強い心的外傷が多いのは、交通事故の被害者です。追突や事故で、身体的痛みや恐怖心が続きます。特に、運転が怖い、常に後ろから追突されるのでは、という恐怖から、運転できない、遠方に行けない、などの後遺症がみられます。運転は日常的な活動なので回避することが難しいようです。症状が長引きやすく数年間以上も続きます。理解されませんが心的外傷の怖さです。
また、長期的外傷体験の継続として、いじめ、仲間外れなどの行動が心的外傷を作ります。
不登校などの原因になります。また、その時を超えても、その後将来にわたり、対人恐怖や警戒心など、生きにくさを作り、時に人間関係の不良が重なり、フラッシュバックが生涯持続する、慢性化した問題を生じる場合があります。
これは幼児期の家庭内での機能不全家庭などでのトラウマが将来にわたり影響を与える例と重なります。
周辺症状として軽症ですが、HSPによる家庭内過敏性も社会での過敏性につながり、人間関係や近所でのトラブル、軽いつまずきや失敗、離婚などのトラブルが心的外傷体験となり、トラウマを作る場合が多いことにも注意が必要です。
家庭のトラブルや学校のいじめなどの問題が尾を引きやすいことに気をつけてください。