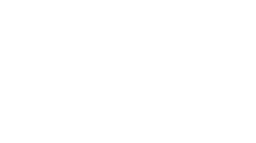2024年01月18日
気候の変化による影響と気象病について
今回のテーマは割とわかりやすく気候の問題についてです。
気候も人間をとりまく大事な環境の要素ですから、この気候の変化が精神面にどのような影響を与えるか考えてみることにします。
外来では、特に若い女性に多いのですが、天気が悪くなったり、気温が急に冷えると、頭痛やめまい、気分の不良、体調の悪化などの症状が強くみられる方が非常に多くいらっしゃいます(通院している若い女性の患者さんのだいたい3分の1から半数ぐらいでしょうか)。
かなり高率で気候に過敏性がある人が多いといえます。
その際、原因としては二つの天気の変化が関係します。一つは1日の中での寒暖の差、つまり日較差(にちかくさ)、もう一つは低気圧の接近や、曇りから雨が降り始めるときなどで、気圧の低下という気圧の変化があらわれるときです。
人間をとりまく環境には、人間関係のみならず、天気、気象という自然環境があります。人間の体は気温の変化や気圧の変化に対応して、自律神経などの働きで体内を一定の環境に保とうとします。
しかし、精神状態が悪く、疲れや神経の過敏性などがその時期に重なると、そのバランスがうまく取れず、体調の不良、悪化をきたします。環境への不適応が生じているからです。
わかりやすいのは生理などの時、体内でのホルモンの変化が起こると、PMS(月経前症候群)などの精神症状を呈することと似ています。身体の中の環境が急激に変化することに、脳の機能の調整が追い付けず、漢方でいうところの、血流、水、リンパの流れなどが変わり、身体のバランスが崩れるからです。この場合は漢方薬の治療が有効です。体のバランスを調整してくれるからです。
寒暖の差で体調の不良がみられるのは、時期があります。特に多いのは4月と11月です。
いずれも、日較差が大きいとき、つまり昼に気温が上がり、朝や夕方に気温が低下する時期です。
「体の調子が悪い」「気分がすぐれない」「うつ的で疲れやすい」「めまいがする」・・・などの症状がみられます。
自分で対策できることとしては、体が冷えないように普段より下着を1枚多く着る、使い捨てカイロなどであたためるなどです。ストレッチ運動などでの予防も必要ですが、クリニックでは漢方薬の投与や安定剤の点滴をします。こうした治療が非常に効果があります。体を冷やさないように注意してください。
次に気圧の変化で起こる体調の不良についてです。
低気圧の接近で起こる体調の不良を、以前NHKでは「気象病」と呼んでいました。
気圧の変化が耳の内耳の血流を変化させ、頭痛とめまいなどが生じるようです(動物の雨に対する回避本能と同じです)。
最近、外来で非常に増えています。
「頭痛」「めまい」の症状を訴える患者さんに「雨」と関係があるか尋ねると、ほとんどの方が「関係ある」と答えます。
昔からあったのでしょうが、あまり気づかれなかったのかもしれません。
NHKが「気象病」と名前をつけたのは約2年前です。その報道で、一般にも理解が深まったようです。
治療としては、水の流れを是正する漢方薬とめまいの薬を併用することで効果があります。
今まで天気の変化に気づかなかった方は、体調の不良の原因にそれが当てはまるかどうか、気をつけて再観察してみてください。