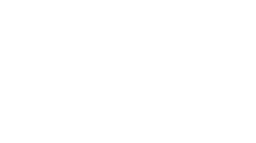2024年01月18日
高齢化と認知症について 第1章:物忘れについて
今回は認知症の問題について考えてみます。
年をとれば脳の働きは落ちます。そして認知症になる、つまりボケるというというのは一般の方々の共通認識といえます。でもこのボケるというのは実際に何を意味するのでしょうか。また、年をとると人間は本当に皆ボケるのでしょうか。
確かに年をとると、50代でも、物覚えは悪くなり、なかなか思い出しにくくなります。「名前が思い出せない、顔は浮かぶけれども・・私もぼけてきたかな。」などという経験をお持ちの方は多いのではないでしょうか。
物忘れが出ると、本人もですが、最初に家族が心配します。脳トレや厳しい見当識(今日は何年何月何日か、今いる所はどこかなど)の質問が飛び交います。そして、少し間違えると叱られます。「ボケたらどうするの」と質問と応答の繰り返し練習と、殺気立った雰囲気が生じやすくなります。本人は委縮します。間違えまいとして緊張して、ますます、間違いやすくなります。
これは、心療内科の受診時にもよく見られる光景です。
まず、物忘れを整理してみましょう。
物忘れには2種類があります。一つは、高齢化すると必然的に起こる記憶の整理棚の混乱です。脳の中にある記憶を整理する棚がしっかりしていれば、一度しまい込んで記憶したことをうまく取り出す、思い出すことができます。しかし、棚が混乱している乱雑であると、顔が浮かぶけれども名前が出ない、など脳の情報をうまく引き出せなくなります。突然思い出したりするのですが、記憶をうまくコントロールできなくなります。
これは病気ではありません。全員に起こる、単なる脳の機能の低下です。記憶の棚の混乱は、身体の筋力が落ちる、行動が遅くなることなどと同じ老化現象の一つなのです。大事なことは、記憶をする(記銘する)ことと、記憶を引きだすこと(想起)は別のことだということです。
覚えること(記銘)自体の障害が認知症なのです。想起の障害の場合の特徴は、本人がよく自分の物忘れを「自覚して」困っていることです。これは正常な反応なのです。
一方、本物の認知症は「覚えること」そのものができなくなります。記憶すること自体ができないのです。
また、記憶に関して、記憶の障害は、近い過去から始まります。今あったことは忘れるけれども、昔の記憶は脳の深いところにしっかり記憶されているので、よく覚えています。ですから、年齢を聞くのがひとつの目安になります。実際は「80歳」であっても、「70歳」と答えるとすれば、10年分は他の記憶も忘れていると思っていいと思います。
10歳以上違っていると、だいぶ症状は進行してきています。記憶が1、2年ずれている場合、認知症の始まりの時期と思ってもらっていいです。「自分の年齢がいくつなのかわからない」と答える頃にはだいぶ進行しています。
また、他に様々な記憶を問うと、「忘れた」と答える場合も多いです。一度覚えたつもりでもすぐに忘れ、むしろそんなことはしていない、聞いていないと言い張ります。
認知症は病識(病的な状態にある人が自分が病気であることを自認すること)がありません。
忘れることがわからないのです。「忘れることはありますか」と聞くと、むしろ否定的に答えたり、返答に窮して黙り込んだりします。時に、何とか切り抜けようとして嘘をつきます。
また、その場では「わかった」と返事をしてもその後忘れてしまいます。これで周囲との関係がこじれます。しかし本人には全く身に覚えがないことなのです。
ここで大事なことは、繰り返しになりますが、二つの現象―いわゆる「高齢化による想起力の低下に基づく物忘れ」と、「病気としての記銘力障害である物忘れ」である認知症を区別することが大事です。「二つの現象は同じではない」ということの理解です。両者の病理は全く違うからです。
人間は年をとると、高齢化のため、知的能力を含めた身体能力が低下します。これは、自然な運命で、誰にも逆らえない自然の摂理です。
老化による機能低下は、刺激の少なさや、楽しみの無さとなど、脳を使わないことも影響します、運動や会話、ゲーム、賭け事などは軽い楽しい脳トレで、脳への良い刺激を与えます。脳を活性化する工夫が必要です。