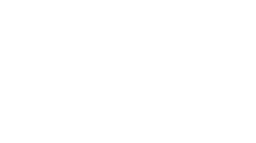2024年02月28日
再考:HSPと機能不全家族、アダルトチルドレンと境界型人格障害について
第1章
このブログの最初のページにHSPという言葉を使って、家族という環境がどのように子供の成長に影響を与えるかを書いてきました。ただ、以前からの心理学の研究などで、家族の問題として、「機能不全家族」や子供の障害として「アダルトチルドレン」、あるいは「複雑性PTSD」「インナーチャイルド」などの言葉や概念があり、そうした研究が大きく進んでいたといえます。
それぞれを取り上げた本により、内容には多少定義に差がありますが、そこでは重篤な問題のある家庭がテーマでした。親からの虐待、ネグレクト、時に「毒親」などと評される親の存在など、明らかな家庭環境の強い負因があり、そうした環境の下では子供に心理的トラウマが生じ、その後の社会への不適応の原因となること、また、子供の発達や性格に対して大きな悪影響を及ぼし、いわゆる「アダルトチルドレン」などの不安定な人格をつくる、という構図が共通の認識でした。
今回、私がHSPという言葉で表現したかったのは、見かけ上それほど問題のない普通の家庭で育ち、特に虐待や毒親でもないのに「過敏で生きにくい」と訴える患者さんが非常に多いことから始まりました(私の場合は境界型人格障害の生じる重篤な家庭構造との比較と症状の類似点が頭にありました)。
そうした患者さんが「自分はHSPでないか」と聞いてくるのです。生きにくさの自覚の表現といえます。
HSP(過敏性)という症状の人にも「幅」があります。正常で、単なる性格的特徴や家庭のしつけやマナーから派生した軽症のものから、「アダルトチルドレン」や「人格障害」といわれる人格の不安定まで重症化するものもあります。ただ、クリニックを受診するのはそれなりの理由や生きにくさが潜んでいます(HSPの患者さんの特徴は最初の章を参照してください)。
私は穏やかな普通の家庭の中にも、強い症状を自覚させる問題が潜んでいることに興味をもちました。
HSPの家庭環境の問題を「機能不全家族」という概念と比較すると、程度の差はありますが、HSPと自覚する人の家庭構造、生きにくさの特徴は軽症です。親どうしの対立などを原因とする、軽い機能不全家族であり、広い意味で機能不全家族の軽症型に分類されると思います。
ただ、違いがあります。家庭という環境の中で、「虐待され、受け身的に我慢して育つ」イメージが強い一般的な機能不全家族の子供に比べると、自分はHSPであると表現する子供は、家庭を支えようとして、むしろ「積極的に、能動的に家庭内の人間関係のトラブルを解消する努力をしている」子供といえます。
現在、以前見られた激越な境界型人格障害(現在の情緒不安定性人格障害と類似)や機能不全の重篤な家庭が減ったように、現代では、3世代同居でも核家族中心の中で、平和で均一な求心力や同調性を求める時代の影響が、家族構造意識の背景にあるのかと思います。平和な安定を求めるがゆえに、家庭内の小さな対立が、子供にはむしろ大きな問題として意識され、自分の家族が壊れずに皆の仲が良くなるように、子供ながら気を使い、無理な努力をしているといえます。
こうして、多少の見る角度の違いにより、「機能不全家族」に対して「HSP」などと表現される病名のできる原因は、昔にさかのぼれば、1980年代頃からの心理学的研究では、「アダルトチルドレン」と呼ばれた患者さんが、精神医学では「境界型人格障害」と呼ばれ、心理学と精神医学でそれぞれ別な角度から同じ対象を研究してきたことと類似していると思います。
私は医師の立場として境界型人格障害の視点から多くの重症者を担当してきました。症状の重さや「境界型人格構造」とも呼ばれた強い人格の不安定さを身に染みる思いで感じてきました。
ただ、当時からも言われていましたが、自傷行為や人格の退行による不安定、二重人格、見捨てられ抑うつ、トラブルの行動化などの境界型の症状は、「アダルトチルドレン」と呼ばれる子供の重症型と同じ症状であるということでした。
私は当時、機能不全家族のことはあまり詳しくありませんでしたが、「境界型人格障害」が問題になり、「家族の環境の問題」が原因で境界型人格障害の症状が発生するのではないかと考えていました(当時精神科では精神病理学という分野に勢力がありましたが、病気の原因や治療法をあまり考えない傾向がありました)。
特に、私の勤務していた山形のような田舎では、3世代同居の家族が多くありました。重症の境界型人格障害の原因として、「強い戦前生まれの祖母が家庭内に君臨し、戦後生まれの母親や子供が人格的におしつぶされてしまう」という悪い家庭環境の下で重症の人格障害が生まれることを多く観察してきました。
最近の10年間、こうした重症の境界型人格障害は、社会や家族の構造の変化に伴い減少してきたといえます。典型的な境界型人格障害(ICD10では情緒不安定性人格障害)は現在あまり見かけなくなりました。時代が移り、家庭の環境が変化したためだと思います。
そうした、臨床の現場の環境の変化を感じていた中で、現在、病院勤務とは違う開業医として患者さんに対応する医療をしていると、HSP症状を訴える患者さんが、外来に大変多くいることがわかりました。特に若い女性に多いといえます。しかもその症状をさらに細かく調べると、昔担当した「境界型人格障害」あるいは別名「アダルトチルドレン」と呼ばれた患者さんの軽症版なのです。確かに全体の人格構造は安定してきています。ただ、症状として自傷行為や強い抑うつ感がみられ、「周囲への気遣い」や「感情の不安定」、「自己評価が非常に低い」などの点がよく似ているといえます。
今、この問題を改めて「機能不全家族」という別の視点の側から見ても、家庭の中に大きな虐待やネグレクト、強い否定はないけれども、軽度の人間関係のひずみや対立などがあり、どこにでもありうる「軽度の機能不全のある家庭構造」が浮かびあがってくるのです。
その際HSPという用語をあえて使う必要はどこにあるのでしょうか。
時代も変化し、以前のように家庭内に戦前の軍国主義時代の世代はいなくなり、家庭の価値観も欧米的な民主主義的価値観に統一され、均一化してきました。しかし同時に、日本的な「協調性」や「同一性」を求める社会の圧力は日に日に高まってきているといえます(余談ですが、社会的には「境界型人格障害」と入れ替わるように、全く別な分野ですが、コミュニケーションや協調性に乏しい「発達障害」の患者さんが大きく浮き彫りになり、クローズアップされてきました)。
そうした時代背景の中で家庭を調べてみると、確かに病気としてのHSP自体の定義はあまりはっきりしているとは言えません。しかしみな、「対人過敏」や「自己評価の低さ」、「インナーチャイルド(自分の中にある「内なる子供」)など、共通の病状や自覚を持つ、まとまりのある一群のグループが確かにあり、HSPは「そのグループのわかりやすい名称」であると理解するといいと思います。
HSPを訴える多くの患者さんの家庭内の環境を調べたところ、人間関係に多少の問題のある家庭ではあるけれども、それほど害のないように見える普通の家庭です。
しかもそこにあるのは、むしろ子供の側が、「対立などの問題のある家庭に適応するために、あるいは家庭を守るために、自分から積極的に努力している」という構図です。
子供は親などからの一方的な虐待を受ける「受け身の被害者」ではなく、「家庭内共同体の一員として、本能的に導かれるような能動的行動で家庭を守ろう」として、家族に多大に「気を使ってきた」と感じられました。
しかもこれは生きていく生物としての、人間にある本能的な行動だと思います。ですから、みな共通の症状を呈するのだといえます。
こうした一群をわかりやすく理解、整理するためにHSPという言葉を借りてきたとも言えます。
ただ穏やかな外見とは別に、心理学的には「インナーチャイルド」と呼ぶべき、自分の人格の中に抑圧されたころの幼児期の人格が二重人格のごとく共存していることも多くみられました。時に激しい怒りや抑うつ気分、希死念慮もそこを源にしているようです。これは「幼児期の我慢、忍耐の結果」を意味します。人格の自然な成長から取り残されたように、現在の人格の中に異物のごとく幼児期の自分が共存し、時に刺激により顔を出すのです。HSPは軽症といいましたが、原因や見かけの症状は軽症でも、人格の面での成長には大きな影響を与えているようです。患者さんに聞くと「自分の中にもう一人の子供の自分がいる」とはっきり答える方が多いです。
幼児期に家庭への適応のために甘えたい自分を抑えて「手のかからないいい子」を演じ、無理して順応してきたため、その自我の一部が成長できずに、大人の自分にそのまま取りこまれている構図でした。この人格の構造はかつての「境界型人格障害」に特徴的に強く認められた「二重人格」とよばれる「怒れる子供」のような人格と現在の人格との共存。さらに、「小さな刺激でその二つが容易に入れ変わるという人格構造」ときわめて類似のものでした。程度は軽症ですが、HSPの患者さんにも境界型人格障害と同じ種類の人格構造がみられるのです。この、成長の中で取り残された子供の頃の自我の名称は、たぶん、心理学的には「インナーチャイルド」という言葉で語られてきた構造と同じなのでしょう。
昔の時代も境界型人格障害の二重人格の爆発トラブルの発生への治療に大変苦労してきました。「人格の再統合」という難しいテーマがあるからです。
HSPの治療でも同じ問題があります。「子供の自我をどのように成長させるか」です。
ただ、結局そうした治療の考え方はシンプルです。親や信頼できる人、あるいは彼氏に自分の症状の基本を理解してもらい、もう一度幼児期の失われた体験を回復し、「甘えによる感情の解放」をやり直すのです。手段は簡単です。心の中にいる3歳児が喜ぶような「頭をなでる、ハグする、膝枕をする」などのスキンシップを通じて信頼を回復することです。現在いくつになろうが、「本人との間で安心した本人の子供がえりを保証し、一時の退行をさせながら、取り残された二重人格を作っている幼児期の自我を解放し、そしてその後ゆっくり見守りながら再成長させる」という根本の治療方針はどちらも同じだと思います。時間はかかりますが、精神面はしっかりと安定します。3歳児に言語は必要ありません。
これは30代、40代になっても同じです。常に心の中の構造は同じなのです。
年齢にこだわらず、恥ずかしいと思わないで、同じようなスキンシップを繰り返すことなのです(別な例で考えれば、恋人同士の親愛の情の交流が退行的に子供っぽく行われのと同じです)。
機能不全家族の側からも同様な症状の子供が多く見いだされると思います。たぶんHSPの概念はその一部を構成し、軽度の機能不全家族の概念と重なる部分も多いかもしれません。今後整理できたらと思います。
第2章
私が次に述べたいのは、自分が医師になったころ「境界型人格障害」と呼ばれた激しい行動化や感情の不安定がみられた一群が、最近かなり消えてしまった理由についてです。
繰り返しで重なるかもしれませんが、もう一度社会の変化という形で再考したいと思います。
「境界型人格障害」は最近のICD診断では「情緒不安定性人格障害」と呼ばれている人たちです。現在、数も減少し行動もマイルドになった印象を受けます。
私が医師になった昭和63年の少し前頃から、アメリカや東京で「境界型人格障害」の存在が認識され(ちなみに私の医局での境界型人格障害認定の第1号は私の受け持ちの患者さんでした)始めましたが、時代的に戦前生まれの祖母がほとんど減少する平成20年頃から大きく減少し、入れ替わるように同時期の平成20年頃から「発達障害」の全盛期に移行してきました。
私は、山形市の中心部にある民間病院で働いていましたが、病院が精神科の救急医療をしていた経緯もあり、全県下から問題のある患者さんが多く紹介されてきたり、患者さんの家族の喧嘩に警察が介入したり、自傷行為などによる救急搬送などで、多くの境界型の人格障害の患者さんが入院してきました。
当時から私が特に人格障害の専門の担当であるように思われていたので、多くの患者さんが集中してきました。それはとてつもなく厳しいハードな医療の連続でした。境界型人格障害の特徴である「人格の不安定」「激越な感情の爆発」「傷つきやすいもろさによる怒り」「度重なる自傷行為」「トラブルの行動化」などが頻回にありました。
家庭環境を調べると、重症の患者さんの多くは、「戦前生まれの祖母と同居し、戦後生まれの嫁である自身の母親と祖母との互いの価値観の相違」が対立の原因になっていたと思います。家庭内の力関係でも強烈で、信じられないような性格の祖母がいて、家庭は破壊され、孫である子供にまで影響し、症状も激越なもので、治療にずいぶん苦労したものです。
見方を変えるとこうした患者さんは広い意味で「機能不全家族」の重症型に含まれていると思います。
時代が進み、戦前生まれの祖母が減少してきた平成20年頃から、こうした重症の境界型の人格障害は大きく減少してきました。家庭内の構造が変わったからだと思います。
それは同時に、境界型の人格障害の発生する原因の一つに、世代間の確執があったということの証明になります。
時代が変わり、強烈な境界型人格障害が減少して、全体として落ち着いてきたのですが、そのころから新しい病気がクローズアップされてきました。「発達障害」です。
出現とともに圧倒的に存在が増加していきました。以前から発達障害の人は多くいたはずですが、それほど問題になりませんでした。忘れっぽいとかの個性の一部という見方だったと思います。
「均一」を求めるその後の社会の変化が、「発達障害」という非社会的障害をあぶりだしてきたとも言えます。昔は、「個性的」とか「自由人」とか言われた人たちが多数含まれていると思います。
昔は発達障害が気づかれず「個性」としてラベルされていた、以前の社会は、振り返れば不安定ではあるが、逆に自由を尊重し、ある意味で個性を許す、許容度の高い社会だったのかと思います。
しかし、発達障害の絶対数が昔よりもなぜこれほど急激に増えたのか、症状が強くなったのか真の原因は不明です。遺伝子の急な変化とみるのもおかしいです。あくまで私見ですが、発達障害の増加の原因は脳の発達の偏りですから、社会環境よりも母胎内に原因があります。日本人の栄養に、農薬や化学薬品などを含めた国外から輸入された食の影響で、変化があるかもしれないと思います。