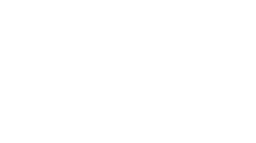2024年03月15日
不安について 第1章:不安障害 不安発作 恐怖症 について
不安は人間の生活に常に付きまとってきます。ここでは不安の問題について考えてみたいと思います。
不安の内容は、第1章では病気としての「不安障害」などの不安全般、第2章では「不安」とトラウマ、第3章では生活者として生きることとしての「不安」、という三つの領域にまたいで論じることにします。
まず、幅の広いテーマですので、生きることの不安を「全般」から見ておきましょう。
人間は誰でも幸福な安全な一生を願って生きています。ただ未来は常に不確実です。
未来に何が起こるかわかりません。
元来、人間は生きる方針を教えられないまま、何が正解かわからず、何も知らないまま生まれ、世界に放り出されて生きているのです。
こうした、「目的がわからず、生きていくことの不安定さ」が根本的な不安を生みます。そうした不確実さの中を生きる「存在」の意味の解析を進めたのが、哲学者のハイデッガーです。
不安のテーマを語ったハイデッガーについては、彼の著書は非常に難しいので、今回は簡単な要点だけにします。
「何も知らない世界に生まれて、生きていくことは常に不安と隣り合わせです。」
「人間はこの不安から逃れるために、時に背徳的生活、精神的に堕落して無関心や刹那的に生きようとする。」と述べます。
ハイデッガーにとって何が大事なのでしょうか。彼が語る存在の意味の一つは、「死を意識し、常に死と対峙して現在、過去、未来を意味づけることであり、それが実存的な人生であり、そうした人間の存在そのものが『現存在』である」ということになります。
ここでは難しくとらえず、生きていることは死と向かい合わせであり、「不安が死の恐怖の問題とつながっている」と理解してください。さらに第3章では、死と向かい合っている生きる生活者として、高齢者のひとたちの日ごろの生活がそれに近いという点を描きたいと思います。
まず不安障害と不安発作、恐怖症についてみていきましょう。
不安と恐怖は隣同士の関係です。互いに合併します。
単純な不安発作に多いのは、「広場恐怖症」、「特異的恐怖症」(特定の場所、物や状況に対し、異常に強い恐怖や不安を抱いたりすること)です。始まりは、「逃げられない場所にいる」と感じるところで生じます。高速道路の長いトンネルや飛行機、電車の中などです。
そうした場所にいて、ふと、何でもないような息苦しさや身体の違和感が生じると、脳の中で危険を察知します。その時に軽い不安が生じます。次に「何か変だ。」「どこへも動けない。」いう閉塞した状況が、閉所恐怖症のようにますます不安を広げます。強い緊張から、さらに原因のわからない「死への恐怖」に広がり、自律神経が興奮し、動悸や頻呼吸、冷や汗などが生じます。
こうした強い違和感、身体症状があるのに、「どこにも逃げられない。」「自分でも何が原因か、何が起こっているのかわからない。」「どうすればいいか対応の仕方がわからない。」のです。さらに不安が強まると、過呼吸によるアルカローシス(二酸化炭素不足)から意識の朦朧、手のしびれなどのパニック障害の症状が発生します。この段階になると救急車による病院への搬送が増えます。このように症状が少しずつ悪化のサイクルに入っていくのです。
このような不安は、不安の生じている途中でも、その「場所」からうまく離れられると症状は改善します。そのため「場面恐怖」とか、ICDの診断では「広場恐怖」あるいは対象が限定された「特異的恐怖症」と呼ばれます。
ただ、一度そうした経験を持つと、不安の意識がトラウマとなり、脳にしっかりと記憶される場合が多くあります。同じ場面や状況に近づくと、そのトラウマの記憶から不安発生への予感が生じ、似たような不安発作の発生への恐怖が生まれます。これが「予期不安」と呼ばれる状態です。
「予期不安」は最初に「悪くなったらどうしよう。」という軽い不安として生じます。次第に頭の中で「悪くなるのではないか。」と想像し、その恐怖が増幅され不安、緊張が高まり、ついに本当の不安発作に達してしまいます。そのため、本人は日ごろから意識的に同じ状況になることを避けようと行動します。例えば車の運転や飛行機など、恐怖を感じた場所や状況を避けるのです。
どうしても避けられず、高速道路などを運転しなければいけない時、強い予期不安が生じやすくなります。この場合も、その後恐怖心から不安発作にまで進みやすいところがあります。本人も理性的には「馬鹿げている。」と思っていますが、予期不安から生じる恐怖への発展には勝てません。理性の暴走といえます。
こうした場合、治療は割と簡単です。理性でのコントロールは難しいのですが、不安薬や抗うつ薬をうまく使うことで、不安に対して非常に効果があります。また、薬を持っているだけで安心して、不安による理性の暴走が食い止められたりもします。
さらによくある一般的な不安の別な例を挙げてみましょう。思春期などに、異性への過剰な意識から「対人緊張」が生じ、不安になる「社会恐怖症」などの場合です。
思春期の若い人では、「小さな失敗」や「異性の視線」が不安の原因になる場合が多くあります。レストランなどで(特に異性のいるところで)、会食していて、緊張から些細な体調の不良や気分の悪化、あるいは赤面した、などが原因で「緊張して食事がうまく取れない。」「嘔吐などが心配でうまく食べられない。」などの「外食恐怖」に発展する例もよくみられます。
また、「相手に迷惑をかける」「場の雰囲気を壊す」「常に嘔吐のことを心配して落ち着かない」など、対人関係に過敏で、「人にどう思われるか常に心配している状態」でも発生しやすいです。「社会恐怖症」と呼ばれます。
同じように対人緊張から生じますが、集団での発表やスピーチなど、目立つ場面で失敗を恐れる心理が働くと、強い不安が発生します。特に異性の視線が気になる思春期には、「見られることそのもの」から不安が生じます。
さらには高い目標達成を課せられたり、過剰に期待されているときにも同じように「期待を裏切るのではないか」または「恥をかくのではないか」などの失敗への恐怖から不安が生じます。
周囲の期待が強い中での、スポーツの試合や試験、仕事の成功なども同じです。高い目標や期待に応えようとするけれども、少し自信がないと、失敗を恐れる感情が生じ緊張します。その緊張感から強い予期不安が生じ、恐怖から自律神経のアンバランスが重なり、不安発作を生じやすくなります。
この場合、大変ですが、対策として「目標を下げること」や「相手ではなく日ごろの自分の力を出すことに集中すること」などを目指すと重圧から少し解放されます。理性的な対応が必要です。特に相手の存在を意識から外し、自分に集中できれば不安は軽くなります。ただ、ほどほどの目標と軽度の不安感は、逆に気持ちや集中力を高め、「負けられない」と気持ちを強くする効果はあります。
「慢性疲労」も原因になります。疲労の中での努力する苦痛がトラウマになり、それが広がると恐怖から強い不安が生じます。これはさらに、疲労の中でも「目標を達成しなければいけない」という焦りが混じると「パニック障害」に広がりやすくなります。そうした恐怖の中で無理をして努力する生活が続くと、家に帰っても恐怖が残ります。
疲れた翌日、職場に戻ることへの恐怖やさらに強い予期不安が生じ、職場に戻ることが困難になり、職場に行けないため休職状態になります。
不安はトラウマと密接な関係にあると述べてきましたが、トラウマは心的外傷の結果としての「負の傷跡の記憶」です。同時に、次の段階ではフラッシュバックなど「危険を警告する本能的な生命の防衛装置の役割」も担っており、個体を危険から遠ざける役割を果たそうとします。不安はその時にトラウマの先駆として「感情」の領域で生じます。そのため、理性でのコントロールが非常に難しいのです。
第2章に続きます。